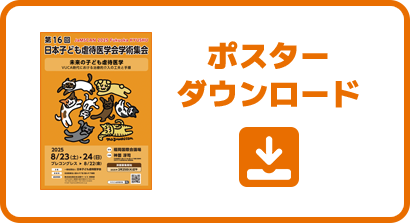ご挨拶
第16回日本子ども虐待医学会学術集会の開催が近づいてまいりました。実行委員とともに、この二年間、福岡での開催に向けて準備を重ねてまいりました。本学術集会を皆さまとご一緒できることを楽しみにしております。
本学会では、「VUCA時代の子ども虐待医学 ― 治療的介入のための工夫と手順 ―」をテーマに掲げ、複雑さと不確実性が高まる現代社会において、子どもとその家族にどのように向き合い、支援の手を差し伸べていくのかを、参加者の皆さまとともに考える機会としたいと願っております。
今年ご準備できたプログラムは、多彩かつ実践的な内容となっております。特筆すべきは、今回は精神科診療の視点をふんだんに取り入れました。子どもの声に耳を澄ませ、「安心」を届け「関係性の信頼」をどのように築くのか。虐待の有無や真偽を超えた、答えのない問いと向き合うことが求められます。家族や養育環境のなかに潜む複雑さと不確実性、そして支援者の側にも生まれる迷いや限界を見つめ直す機会にしていただければと考えております。
プログラムには、特別講演2編、共催セミナー2編、国際シンポジウム1編、子ども虐待法的対応セミナー1編、教育講演7編、シンポジウム12編、Up to Date レクチャー16編 をご用意し、分野横断的なテーマを幅広く取り上げております。現場で役立つ知見とともに、制度や教育の次世代への継承を見据えた議論を共有できる場となるよう準備を重ねてまいりました。
初代理事長・小池通夫先生のもとで、北九州市立八幡病名誉院長 市川光太郎先生らを中心に2009年8月2日に「日本子ども虐待医学研究会」が正式に設立されました。小池先生は設立趣意の中で、次のように記されています。「(抜粋)虐待の問題を自由に、かつ専門的に議論できる場はきわめて限られている。子ども虐待における医学的な取り組みの向上と子ども虐待に関する調査・研究ならびに知識の普及をはかり、関係機関と連携して虐待・ネグレクト家庭を支援し、子ども虐待予防を推進することを目的とし、さらに、専門職の育成を目指し、わが国における子ども虐待を専門的に研究する団体として「日本子ども虐待医学会」を設立する。」この理念に支えられ、本学会は医療の専門性を軸としつつ、福祉・教育・司法との対話を大切にしながら、虐待医学という実践知を社会に根づかせてきました。
研究会としてうぶ声をあげた第1回から第3回学術集会は、まさにこの福岡・北九州の地で開催されました。 今回の学術集会は、その原点に立ち返ると同時に、「次の15年」を切り拓く新たなスタートとして位置づけております。
今回の学術集会は、子どもの権利に関する国際シンポジウム、法的対応セミナー、オンライン配信限定の教育講演など、参加者の皆さんとともに新たな担い手とのつながりを育む取り組みにも力を入れたいと思います。これまで学会を支えてくださった皆さまへの深い感謝を込めつつ、子どもの声が確かに届く社会に向けた一歩を、皆さまと共に踏み出せればと願っております。九州福岡の地で、そしてオンラインで多くの皆さまとお会いできますことを、心より楽しみにしております。今後とも温かいご支援とご参加を、どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和7年7月15日 第16回日本子ども虐待医学会学術集会
大会長 神薗 淳司