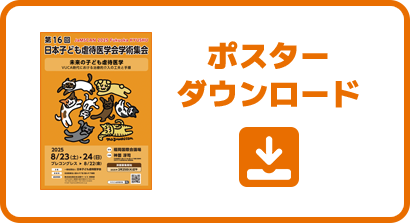プログラム
プレコングレス
虐待対応プログラム BEAMS Stage 1
8月22日(金) 14:00〜15:00 中会議室 502+503
虐待対応プログラム BEAMS Stage 2
8月22日(金) 15:10〜16:40 中会議室 502+503
AHT研究部主催 第14回シンポジウム
8月22日(金) 14:00〜16:30 国際会議室 501
ケースレビュー委員会主催 第24回事例検討会
8月22日(金) 17:00〜20:30 国際会議室 501
※AHT研究部主催 第14回シンポジウム、ケースレビュー委員会主催 第24回事例検討会は当日参加はできません。
BEAMS Stage 1,2は、当日参加は可能です。
特別講演
特別講演1 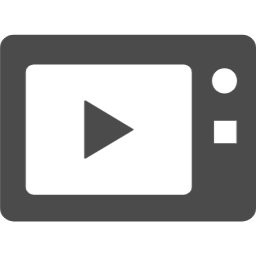 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月23日(土) 13:40〜14:40「国際会議室501」
「⼦ども虐待の発⽣メカニズムと影響を探る」
- 座⻑:
- 井上 登⽣(中津こどもメディカルスーパーバイザー)
- 演者:
- 黒⽥ 公美(東京科学⼤学 ⽣命理⼯学院)
本講演では、⼦どもの愛着形成における不適切な養育の影響を、霊⻑類モデルを⽤いて明らかにした研究、⼦ども虐待加害者の背景要因をDevelopmental Pathway解析により検証した調査結果、さらに虐待関連の公的統計調査の深掘りの重要性について解説します。幼少期の虐待経験、家庭機能不全がもたらす社会的影響、そして⾮⾎縁成⼈との同居が重度虐待に与える寄与度を議論し、虐待予防策の科学的根拠を提供します。
「子どもの心」相談医研修単位(申請中)
日本小児科学会 小児科領域講習(申請中)
特別講演2 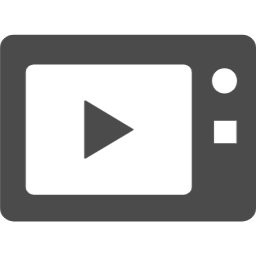 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月24日(日) 10:40〜11:40 「国際会議室501」
「ICD-11におけるcomplex PTSD:児童期マルトリートメントの短期・⻑期的影響」
- 座⻑:
- ⼤治 太郎(聖ルチア病院)
- 演者:
- ⼤江美佐⾥(久留⽶⼤学医学部神経精神医学講座)
子どものこころ専門医更新講習認定(申請中)
教育講演
教育講演1 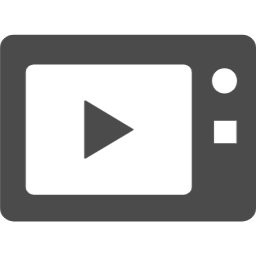 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月23日(土) 12:30〜13:00 「中会議室502+503」
「体重増加不良の中に潜む鑑別が重要な⼩児の消化器疾患」
- 座⻑:
- 岡⽥あゆみ(岡⼭⼤学病院 ⼩児医療センター⼩児⼼⾝医療科)
- 演者:
- ⽔落 建輝(久留⽶⼤学⼩児科学教室)
教育講演2 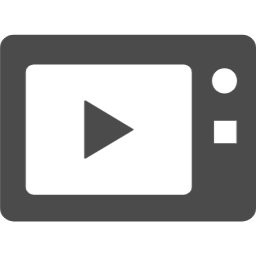 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月23日(土) 13:00〜13:30 「中会議室502+503」
「成⻑・体格の異常を⾒逃さない:疾患と養育環境問題の早期発⾒の鍵」
- 座⻑:
- 岡⽥あゆみ(岡⼭⼤学病院 ⼩児医療センター⼩児⼼⾝医療科)
- 演者:
- ⼭本 幸代(産業医科⼤学医学部医学教育担当教員)
教育講演3 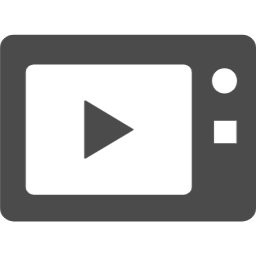 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月23日(土) 13:40〜14:40 「中会議室502+503」
「性暴⼒被害者⽀援における産婦⼈科医の役割」
- 座⻑:
- ⼩川 厚(福岡⼤学筑紫病院)
- 演者:
- 坂井 邦裕(⻄福岡病院 婦⼈科)
教育講演4 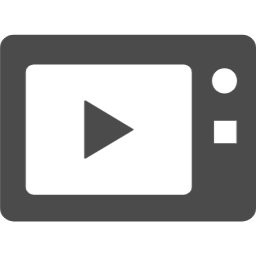 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月24日(日) 08:00〜08:50 「国際会議室501」
「救急外来の関わりが⼦ども⽀援につながるには 〜⼦育て⽀援の全体像から具体的な声かけまで〜」
- 座⻑:
- 古野 憲司(福岡⾚⼗字病院)
- 演者:
- 中村俊⼀郎(慶応義塾⼤学⼩児科)
教育講演5 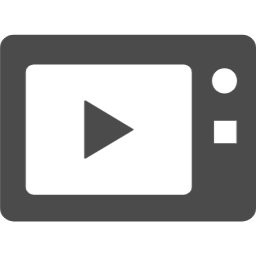 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月24日(日) 08:00〜08:50 「中会議室502+503」
「⼦ども虐待と⾻・軟部組織超⾳波検査〜こども達の代弁者となるために〜」
- 座⻑:
- 横井 広道(四国こどもとおとなの医療センター⼩児整形外科)
- 演者:
- ⼩野 友輔(北九州市⽴⼋幡病院 ⼩児臨床超⾳波センター)
教育講演6 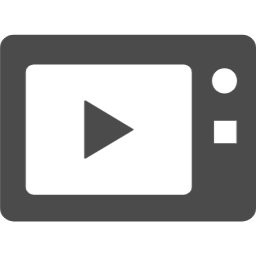 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月24日(日) 10:40〜11:40 「中会議室502+503」
「虐待対応で知っておきたい凝固異常〜家族に不要な負担をかけないために〜」
- 演者:
- ⽩⼭ 理恵(産業医科⼤学 ⼩児科学教室助⼿・⾎友病センター)
日本小児科学会 小児科領域講習(申請中)
教育講演7 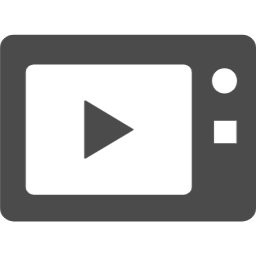 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月24日(日) 12:00〜13:00 「中会議室502+503」
「⻭科受診⾏動や⼝腔症状を通して考える⼦ども達の⽣活環境」
- 座⻑:
- 岩原 ⾹織(⽇本⻭科⼤学 ⻭科法医学)
- 演者:
- 岡 暁⼦(福岡⻭科⼤学 成⻑発達⻭学講座成育⼩児⻭科学分野)
日本小児科学会 小児科領域講習(申請中)
共催セミナー
共催セミナー1
8月23日(土) 12:30〜13:30 「国際会議室501」
「⼦育てに役⽴つ漢⽅」
- 座⻑:
- 稲光 毅(いなみつこどもクリニック)
- 演者:
- ⼩川 恵⼦(広島⼤学病院 漢⽅診療センター)
- 共催:
- ミヤリサン製薬株式会社
共催セミナー2
8月24日(日) 12:00〜13:00 「国際会議室501」
「親のパーソナリティ障害と神経発達特性」
- 座⻑:
- ⼩曽根基裕(久留⽶⼤学医学部神経精神医学講座)
- 演者:
- 辻井 農亜(富⼭⼤学⼦どものこころと発達診療学講座)
- 共催:
- 武田薬品工業株式会社
国際シンポジウム 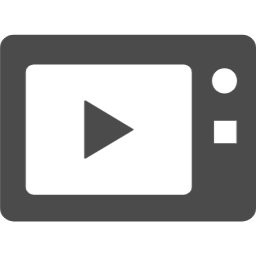 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月24日(日) 09:00〜10:30 「国際会議室501」
「子ども虐待医学と子どもの権利」
- 座 長:
- ⼭⽥不⼆⼦(認定NPO チャイルドファーストジャパン)
- シンポジスト:
- 奥⼭眞紀⼦(山梨県立大学大学院人間福祉学研究科)
Bruce Adamson(Past Children and Young People’s Commissioner cotland)
⼭⼝ 有紗(⼦どもの虐待防⽌センター・国⽴成育医療研究センター社会医学研究部)
本国際シンポジウムでは、⼦ども虐待医学の視点から「⼦どもの権利」を捉え直し、医療・制度・国際的実践をつなぐ対話の場を⽬指します。座⻑は、⻑年にわたり⼦ども虐待医学と⽀援の実践と啓発に取り組んでこられた⼭⽥不⼆⼦先⽣が務めます。奥⼭眞紀⼦先⽣からは、パリ原則や児童の権利に関する条約(CRC)の批准以降、こども基本法制定・こども家庭庁設置に⾄る国内の歩みが語られ、現在も未整備の⼦どもコミッショナー制度の課題が提起される。続いて、前スコットランドの⼦どもコミッショナーBruse Adamson⽒によるビデオメッセージを通じて、⽇々の実務や制度運⽤の⼯夫、そして⽇本への⽰唆が紹介される。⼭⼝有紗先⽣からは、⼩児医療や福祉の現場における⼦どもの権利の保障、⼦どもの声に寄り添う実践のためにできること、それを⽀える制度的な基盤のあり⽅について提⾔がなされる予定である。
子どものこころ専門医更新講習認定(申請中)
「子どもの心」相談医研修単位(申請中)
⼦ども虐待法的対応セミナー
8月23日(土) 10:40〜12:10 「中会議室502+503」
「教えて!医療現場の法的対応〜現場での疑問から民法改正(離婚後の共同親権等)に関する最新の問題まで〜」
- 座 長:
- 一宮里枝子(福岡県福岡児童相談所 児童福祉法務専門監 弁護士)
- シンポジスト:
- 森吉 研輔(北九州市立八幡病院 小児科)
久保 健二(福岡市こども総合相談センター常勤弁護士)
児童虐待対応において、病院は児童相談所から意⾒や書⾯を求められることは少なくない、児童相談所は何を求めているのか?といった疑問や、そのほかにも⼦どもと保護者の⾯会はどう対応するべき?など⽇々感じている疑問、そして、この先、⺠法改正によって訪れる⽗⺟の共同親権など、医療現場での児童虐待対応における法的対応に対する疑問や課題を、児童相談所の弁護⼠と共に検討し、より理解を深めていきたい。
シンポジウム
シンポジウム1 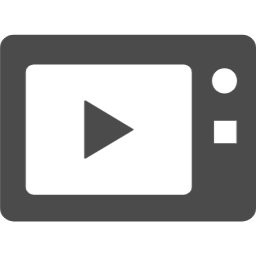 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月23日(土) 09:00〜10:30「国際会議室501」
「周産期のメンタルヘルスケアと子どもの虐待予防」
- 座 長:
- 中村俊一郎(慶應義塾大学医学部小児科)
本田しのぶ(福岡赤十字病院 小児科病棟看護師) - 基 調 講 演 :
- 山下 洋(九州大学病院 子どものこころの診療部)
- シンポジスト:
- 児玉 春菜(福岡赤十字病院 産婦人科病棟)
菊本絵万里(産前・産後母子支援センター Comomotie)
新しい命をむかえ親となることは、それまで築いてきた⽣活基盤や家族関係から⼤きく変化する場⾯である。育児の原点ともいえる周産期において、スムーズな第⼀歩が踏み出せるように⽀援することが重要である。若年妊娠、予期せぬ妊娠、養育者の知的・精神障害による育児困難、養育者⾃⾝が抱える幼児期の愛着障害など、虐待へつながる背景要因は多岐にわたる。特定妊婦に対する関わりは、妊婦⾃⾝からの相談だけではなく医療機関及び地域⾏政機関による積極的な関わりが不可⽋である。また特定妊婦だけでなく、現代社会における育児環境の孤独さや経済的基盤の不安定さなど様々な不安要素が、多くの養育者のメンタルヘルスに影響を及ぼしている。⺟親だけではなく家族への総合的なサポート体制を社会全体で構築していくことが求められている。本セッションでは、虐待リスクのある妊産褥婦を⾒逃さずに周産期から切れ⽬なく関わり続けることで虐待へつなげないための取り組みについて考える。
子どものこころ専門医更新講習認定(申請中)
シンポジウム2 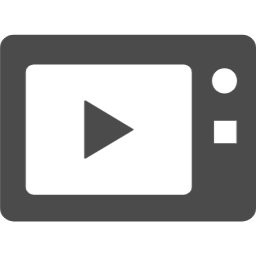 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月23日(土) 10:40〜12:10 「国際会議室501」
「スペシャルニーズのある子どもたちの居場所をデザインする~周産期と地域での実践~」
- 座 長:
- 荒木 俊介(はぐむのあかりクリニック)
勝連 啓介(発達相談クリニックそえ~る) - シンポジスト:
- 網塚 貴介(青森県立中央病院)
丸山 有子(いまきいれ総合病院)
金原 洋治(かねはら小児科)
金子 淳子(金子小児科)
医療的ケアや神経発達症などスペシャルニーズのある⼦どもたちは不適切な養育を受けるリスクが⾼く、⽀援が必要な家庭が少なくない。周産期センターや地域の⼩児科医の取り組みを紹介し、⼦どもたちが安⼼して成⻑できる居場所づくりを考え、拡げるきっかけとなることを⽬指す。
「子どもの心」相談医研修単位(申請中)
シンポジウム3
8月23日(土) 14:50〜16:20 「国際会議室501」
「気になった!さあ、どうしよう? ―看護職にできる養育者支援―」
- 座 長:
- 長友 太郎(福岡赤十字病院)
梶原 陽子(福岡赤十字病院) - シンポジスト:
- 定栄 千佳(福岡赤十字病院)
村山 順子(福岡大学病院)
青野 広子(福岡看護大学)
松岡ちずよ(真田産婦人科麻酔科クリニック)
黒川美知子(くろかわみちこ小児科クリニック) - 指定討論者:
- 松本 宏美(福岡市南区保健福祉センター)
⼦ども虐待予防・対応において、⼦どもとその親への⽀援は⼩児看護の重要な役割のひとつである。しかし養育者⽀援の視点でいうと、現場では難しさを抱いている現状にある。そこで本シンポジウムでは、各施設の取り組みの現状と課題を共有し、看護師にできる養育者⽀援の在り⽅について考えていく場としたい。
シンポジウム4 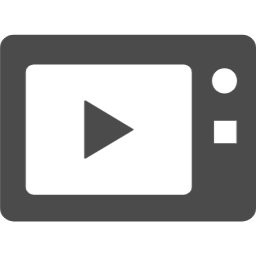 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月23日(土) 16:30〜18:00 「国際会議室501」
「虐待の背景で押さえておきたい精神医学 〜親の精神疾患から希死念慮の対応まで〜」
- 座 長:
- 松岡美智⼦(久留⽶⼤学神経精神科)
菊地 祐⼦(⼦どもと家族のメンタルクリニックやまねこ) - シンポジスト:
- 箱島 有輝(国府台病院 児童精神科)
⽯⽥ 哲也(久留⽶⼤学神経精神科)
千葉⽐呂美(久留⽶⼤学神経精神科)
吉村 裕太(福岡⼤学精神神経科)
精神疾患を持つ親と共に暮らす⼦どもの置かれる⽴場や影響について概説し、不安障害・アディクション(依存症)・発達障害と⼦育てへの影響について事例を交えて解説する。⽀援者が迷いやすい⼦どもの希死念慮に関する考え⽅や対応を学び、⼦どもの状況に気づいた⼤⼈に何ができるのか具体的な⽅策を検討する場としたい。
子どものこころ専門医更新講習認定(申請中)
シンポジウム5 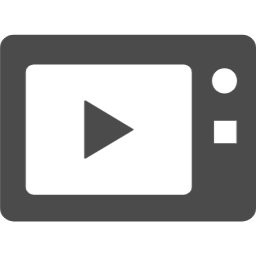 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月23日(土) 9:00〜10:30 「中会議室502+503」
「性虐待診療の現場から見える課題と展望〜それぞれの立場から〜」
- 座 長:
- 川口 真澄(那覇市立病院)
木下あゆみ(四国こどもとおとなの医療センター) - シンポジスト:
- 溝口 史剛(高崎総合医療センター)
三浦 耕子(沖縄県立中部病院)
菊地 祐子(子どもと家族のメンタルクリニック やまねこ)
上野 里恵(日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 看護部)
シンポジウム6 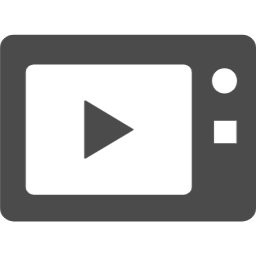 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月23日(土) 14:50〜16:20 「中会議室502+503」
「医療と児童相談所の連携~児相が求める連携とは?~」
- 座 長:
- 森吉 研輔(北九州市立八幡病院 小児科)
一宮里枝子(福岡県福岡児童相談所 児童福祉法務専門監 弁護士) - シンポジスト:
- 松尾 正和(福岡県福岡児童相談所 相談第一課)
濱畑 善行(福岡市こども総合相談センター こども緊急支援課)
守田 敬一(北九州市子ども総合センター 児童虐待対策担当課) - 指定討論者:
- 石倉亜矢子(函館中央病院 小児科)
昨今、児童虐待対応において他機関・多職種による連携は⽋かせないものとなっており、特に、児童相談所と医療の対応が児童の⽣命・⾝体を守る⼤きな要となるケースも少なくない。しかし、⽴場の異なる機関が連携しあうには様々な課題が伴う。福岡県内の3児童相談所から医療連携が必要とされた事例を紹介し、各機関ができること、できないこと、そしてお互いが求めあうものを確認しつつ、医療と児同相談所の連携体制の在り⽅について追求したい。
シンポジウム7
8月23日(土) 16:30〜18:00 「中会議室502+503」
「被虐待児の診療録記載のポイントと開示請求への対応」
- 座 長:
- 石倉亜矢子(函館中央病院 小児科)
丸山 朋子(大阪急性期・総合医療センター 小児科・新生児科) - シンポジスト:
- 本山 景一(茨城県立こども病院 救急集中治療科)
橋倉 尚美(社会医療法人愛仁会高槻病院)
福田 育美(四国こどもとおとなの医療センター地域医療連携室)
根ケ山裕子(名古屋市西部児童相談所 弁護士)
被虐待児を診療する際、⼦どもや保護者の語った⾔葉を医療者が要約することなく、そのまま記録すること、全⾝の⾝体所⾒を詳細に記録し、体表写真を記録に残すことも重要とされています。被虐待児の場合、複数の診療科の医師が診療にあたることが多く、重症児の場合にはしばしば⼊院期間が⻑く、診療録は膨⼤です。また、医のみではなく、看護師、公認⼼理師、保育⼠、リハビリテーションスタッフ、医療ソーシャルワーカーなど多職種の記録とともに、院外の関係機関、児童相談所や市町村、警察、検察等との会議内容なども記録されています。そして、この記録は、被虐待児の医学的な評価、児童福祉対応、裁判において重要な証拠となります。
しかし、刑事裁判では診療録の⼀部が切り取られ、誤った解釈がなされるケースも⽣じています。さらに、保護者からの診療録開⽰請求が⾏われ、保護者側の弁護⼠による医療機関批判に利⽤される懸念もあります。また、関係機関が提供した情報が診療録に記載されていた場合、診療録開⽰により、思わぬ形でその内容が保護者に知られてしまい、関係機関との間でトラブルが⽣じたり、その後の⽀援が困難になることがあります。診療録の適切な記載⽅法、開⽰請求への対応について、現状の課題について多職種で議論し、今後、現場で困らないように、迷わず対応できるようにするための第⼀歩にしたいと考えます。
日本小児科学会 小児科領域講習(申請中)
シンポジウム8 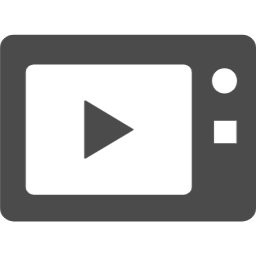 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月24日(日) 13:10〜14:40 「国際会議室501」
「子ども虐待事例データバンクへの症例登録と登録データを用いた臨床研究」
- 座 長:
- 安 炳文(京都第一赤十字病院)
内ケ崎西作(東京医科大学 法医学分野) - シンポジスト:
- 山本 英一(愛媛県立中央病院 小児科)
高橋 英城(滋賀県立総合病院 内分泌代謝糖尿病科)
石川 順一(大阪市立総合医療センター 小児救命救急センター)
富永 禎弼(東京女子医科大学附属足立医療センター 脳神経外科)
栗原八千代(聖マリアンナ医科大学 小児科)
小川 優一(千葉県こども病院 救急総合診療科)
シンポジウム9 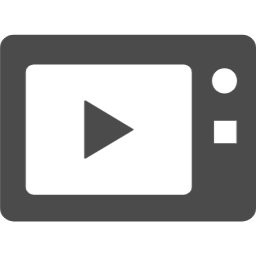 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月24日(日) 14:50〜16:20 「国際会議室501」
「子ども虐待に対応する医師に求められる医師像とは?」
- 座 長:
- 古野 憲司(福岡赤十字病院)
- シンポジスト:
- 井上 登生(中津こどもメディカルスーパーバイザー)
米山 法子(市立秋田総合病院)
岡田あゆみ(岡山大学病院)
橋倉 尚美(高槻病院)
シンポジウム10
8月24日(日) 09:00〜10:30 「中会議室502+503」
「重篤事例急性期の現状と捜査機関との連携(小児救急・集中治療の現場から)」
- 座 長:
- 安 炳文(京都第一赤十字病院 救急科)
武藤雄一郎(熊本赤十字病院 小児科) - シンポジスト:
- 起塚 庸(高槻病院 PICU)
山上 雄司(兵庫県立尼崎総合医療センター 小児救急集中治療科)
賀来 典之(九州大学病院 救命救急センター)
西賴 慎悟(福岡県警察本部刑事部捜査第一課)
シンポジウム11 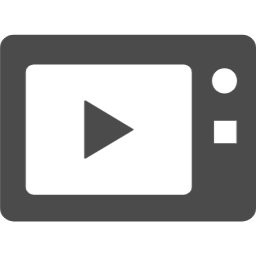 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月24日(日) 13:10〜14:40 「中会議室502+503」
「性虐待対応における本邦の現状とCAC 設立に向けた取り組み」
- 座 長:
- 小川 優一(千葉県こども病院)
福田 育美(四国こどもとおとなの医療センター) - シンポジスト:
- 本山 景一(茨城県立こども病院)
田上 幸治(神奈川県立こども医療センター)
毎原 敏郎(兵庫県立尼崎総合医療センター)
守谷 充司(仙台市立病院)
本邦では性虐待を受けた子どもに適切に対応できているとは言い難い現状がある。CAC(Children’s Advocacy Center)は、被害を受けた子どもが司法面接、系統的全身診察、心のケアをワンストップで受けられる施設である。本邦での医療機関をハブとしたCAC設立に向けた取り組みを紹介し、改善点と課題について検討したい。
シンポジウム12 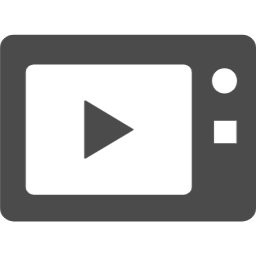 オンデマンド配信有
オンデマンド配信有
8月24日(日) 14:50〜16:20 「中会議室502+503」
「気づきから始まる看護師業務とシステム化の工夫」
- 座 長:
- 梶原 多恵(北九州市立八幡病院)
木島久仁子(群馬県立小児医療センター) - 指 定 発 言:
- 毎原 敏郎(兵庫県立尼崎総合医療センター)
- シンポジスト:
- 橋本 優子(北九州市立八幡病院)
時津 晴美(飯塚病院)
平方多美子(J CHO九州病院)
藤田めぐみ(福岡大学病院)
野中 美喜(福岡市立こども病院)
⼩児医療の現場では、看護師による「違和感」や「気づき」が、虐待やネグレクトの早期発⾒、安全管理、家族⽀援などに直結する重要な情報源となる。しかし、こうした気づきは、⼗分に⾔語化・記録化されず、組織としての知⾒や対応⼒の向上に活かされないことも多い。本シンポジウムでは、福岡県内の5施設が、それぞれの看護業務における「気づき」の共有⽅法、チームとしての対応、教育研修、さらには仕組み化・制度化に向けた取り組みを報告する。具体的には、⼩児救急における即時的な判断と地域との連携、成⼈外来に同伴した⼦どもに対する偶発的な気づきと体制整備、医療的ケア児の⽣活環境での継続的な⾒守り、⻑期フォローを前提とした外来看護におけるCPTとの連携、そして気づきを可視化し活⽤するための教育・啓発ツールの⼯夫など、多⾓的な実践が紹介される。本シンポジウムを通じて、看護師が抱く「この⼦、気になる」という感覚を、いかにチームで共有し、現実の対応や制度へと昇華させていくかについて、多施設の知恵と⼯夫を学び合い、現場に還元可能な知⾒を得ることを⽬的とする。
「子どもの心」相談医研修単位(申請中)
Up to Date レクチャー(オンデマンド配信)
「骨折のメカニクス」
- 演者:
- 福水 希梨(熊本赤十字病院 救急科)
「小児頭部外傷の特徴 -AHTの管理・予後を含めて」
- 演者:
- 下川 能史(マギル大学モントリオール神経学研究所・病院 脳神経外科
(九州大学大学院医学研究院脳神経外科))
「周産期感染および性感染症と虐待」
- 演者:
- 荒木 孝太郎(沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児総合診療科)
「乳幼児の体重増加不良」
- 演者:
- 鳥尾 倫子(福岡市立こども病院 総合診療科)
「易骨折性の鑑別診断:骨系統疾患とその他の骨脆弱性疾患」
- 演者:
- 中村 幸之(福岡市立こども病院 整形・脊椎外科)
「家族病理を探る──不登校と起立性調節障害の交差点にあるもの」
- 演者:
- 石井 隆大(久留米大学医学部 小児科学講座)
「(小児救急)SIDSと突然死の基礎知識」
- 演者:
- 沖 剛(北九州市立八幡病院 小児科)
「まず知っておきたい 自傷・オーバードーズ 対応の基本」
- 演者:
- 大平 智子(宮崎県立宮崎病院 小児科)
「頭部画像」
- 演者:
- 一宮 優子(福岡歯科大学小児科学分野)
「腹部鈍的外傷と子ども虐待」
- 演者:
- 嘉村 拓朗(飯塚病院 小児科)
「(外来小児科)子ども虐待:プライマリケアでの気づき」
- 演者:
- 諸岡 雄也(諸岡小児科ちくし通りクリニック)
「口腔内損傷を通して虐待を考える」
- 演者:
- 柏村 晴子(福岡歯科大学医科歯科総合病院)
「骨軟部組織領域における超音波診断の現在地
―小児虐待画像診断における可能性を見据えて―」
- 演者:
- 江口 啓意 (北九州市立八幡病院 小児科)
「薬物中毒と虐待 ~Child Protection Teamの介入を依頼したジフェンヒドラミン中毒から学ぶ~」
- 演者:
- 玉井 資(大分こども急性救急疾患学部門医療・研究事業)
「月経前症候群・月経前不快気分障害(PMS・PMDD)と児童虐待リスク
―思春期からの早期介入の重要性―」
- 演者:
- 木下 雅(久留米大学産婦人科学教室)
「子ども虐待とジェンダー」
- 演者:
- 矢野 庄一郎(のぞえ総合心療病院)